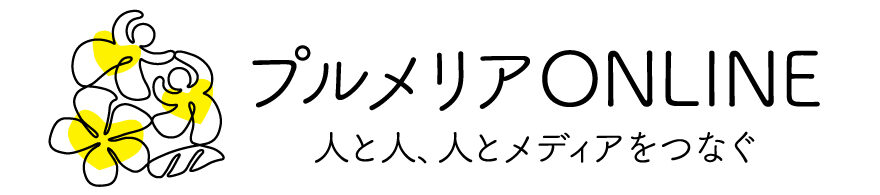鄧小平の「遺言」を反故にした習近平の末路
東京国際大学 国際関係学部 教授 河崎眞澄
(不動産経済Focus & Research 2025.7.23掲載)
経済大国を目指した鄧小平
「もしも中国がある日、変節して超大国となり、世界の覇権を握って侵略や搾取をするようになることがあれば、世界の人民は中国を『社会帝国主義だ』と見なし、中国の悪事をあばき、そして中国に反対し、中国人民と力を合わせて(中国の社会帝国主義を)打倒すべきだ」
信じられないだろうが、かくも厳しい指摘は、かつて中国共産党の最高指導者でもあった鄧小平が1974年4月、国連の資源総会に中国代表団長として出席したときの演説の一説だ。当時はなお、毛沢東の扇動に陶酔した10代を中心とした「紅衛兵」と呼ばれた暴力的な集団が、政財界の実力者を吊るし上げる「文化大革命(文革) 」が、全土に吹き荒れていた時期でもあった。
文革は、政治や経済の近代化と自由化に目を向けはじめていた中国共産党幹部を「政敵」と考えた毛沢東が、党内粛清のため、若者の愛国心を利用した権力闘争だった。この文革の一時期、失脚していたものの這い上がりつつあった鄧小平は国連演説で、この権力闘争がいずれ終わり、中国は「資本主義を導入して経済大国になる」との可能性も、国際社会に示唆していた。
76年の毛沢東死去で文革が終わり、78年末の重要会議で経済成長を優先させる改革開放路線にカジを切ったのが、鄧小平だった。日本のみならず欧米も80 年代から90年代に、経済発展さえすれば中国も成熟し国際社会と共同歩調を取り、民主化に向かうと期待した。日本は総額4兆円近い政府開発援助(ODA) を対中供与した。89年6月、民主化を求めた多数の学生らを人民解放軍が弾圧し、殺傷した「天安門事件」は国際社会を震撼させたが、それでも2010年には名目国内総生産(GDP)で日本を追い抜く世界第2位の経済大国になった。
共産党一党支配の中国で鄧小平は、天安門事件で殺戮を演じながらも、「社会主義市場経済」という、一見すると矛盾した政策にも見える看板を強調した。1992年を境に、豊かな経済を望む人民を鼓舞しはじめ、外資導入と輸出拡大を急いだ。その真意は「(天安門事件のような問題を起こして)共産党の一党支配は絶対に揺るがすな。その代わり中国人民には貧困から脱却し、外資を利用して経済的にどんどん豊かになってもらうことを約束する」ことにあった。
人口が14 億人を超えた現在の中国では、少なく見積もっても沿岸地域など都市に暮らす5億人近くは中産階級から富裕層とみていいだろう。農村に生まれ農村戸籍しか持てない数億人を事実上の内陸植民地人として搾取し、都市戸籍の人々は不動産売買や輸出入、外資からの搾取などで富を得た。1億人超の共産党員も自らビジネスを手掛け、同時に巨額の賄賂も懐に収めて「経済大国」の豊かさを満喫した。いずれは米国経済すら追い抜く、はずだった。
ひずみが見えはじめた習近平政権
その鄧小平の「遺言」ともいえた路線と約束を守ったのは、後継者の江沢民と胡錦濤だけだった。2012年に党総書記に上りつめ、13年に国家主席も兼務した習近平はむしろ国際社会との協調を徐々に弱めて日米欧を敵対視し、党内の意思決定を鄧小平が定めた集団指導体制から独裁体制に切り替えた。習近平の「政敵」だったエリート集団「中国共産主義青年団」出身者の前首相の李克強などは退任後、23年10月に68歳の若さで謎の死を遂げている。
需給バランスを無視した過剰な建設で、不動産市況が極端に悪化する中で、20年に湖北省武漢が感染源だった新型コロナのパンデミック(世界的大流行)によるロックダウンの影響も深刻化し、中国経済は統計数字以上に落ち込んでいるのは周知の事実だ。さらに日本やドイツの自動車産業を狙い撃ちしたEV(電気自動車)産業の育成と国内市場拡大の政策も、過剰生産やバッテリーの相次ぐ発火事件、充電施設不足と奪い合い、電力供給網の未整備など、あらゆる政策が追い付かず、EVトップ企業のBYDなどは「経営破綻した不動産大手、恒大集団の二の舞」ともいわれはじめた。過大な設備投資が隠れ債務を雪だるま式に増やし、もはや国有銀行に共産党がいくら命じても巨額債務の棒引きは不可能。債務不履行や経営破綻は避けられなくなる。
むろん、これで中国経済そのものが破壊されるわけではないが、打撃を最も被るのは鄧小平の約束を破った習近平の政治基盤と考えるのが自然だ。「政治の不自由と引き換えに、経済的豊かさを享受した」数億の民は、「豊かさが消えて債務が山積み」となれば、政治経済社会から軍事まで全ての権力を一身に集める習近平その人に、怒りをぶつけることは疑う余地がない。
共産党内部もそうした中国社会の動きに敏感だ。さもなくば習近平のみならず、一党支配そのものも崩壊しかねない。この6月に行われた共産党政治局の会議では、鄧小平が継続を強く求めた「集団指導体制」、すなわち独裁制の排除に回帰することまで示唆する決定を行った。習近平に粛清された共青団や軍幹部らの復帰も、徐々に進む。このことは習近平の権力基盤弱体化や政権交代すら予感させる。党内にも危機感と同時に恨みのマグマが充満しているからだ。
暗雲立ち込める習近平の今後
5年に1度開かれる中国共産党の党大会は2年後の27年秋に予定されている。習近平は22年に極めて異例ながら総書記3期目を勝ち取ったが、27年には4期目を無事に迎えることができるかどうか、微妙な情勢ともいえる。当初は毛沢東のような終身の最高権力を狙っていたであろう習近平の命運が、現在進行形の中国経済弱体化によって大きく揺らいでいることもまた、疑う余地はない。トランプ政権の対中関税政策や対中包囲網の形成も今後、習近平の政治生命を縮める要因になるかもしれず、「窮鼠猫を噛む」ような対外攻撃すら懸念される。
天安門事件で軍隊派遣を命じ、民主派を求める学生らを弾圧した鄧小平もまた、共産党の最高実力者ではあったが、それでも「独裁」が中国のためにはならず、国際社会との連携のなかでの協調や集団指導体制による合議制によって、中国の暴走を防がねばならないことを、半世紀以上前に予言していた。その鄧小平の遺言と、鄧小平による中国人民への約束を守れなかった人物が、どこまで共産党内と14億人の民を統治し続けられるか。まだ、だれも予言できない。
関連リンク
不動産経済Focus & Research 刊行物一覧 (fudousankeizai.co.jp)
プルメリアでは多岐にわたるテーマとスピーカーによる講演・セミナーをアレンジしています。ご相談は、こちらよりお問い合わせください