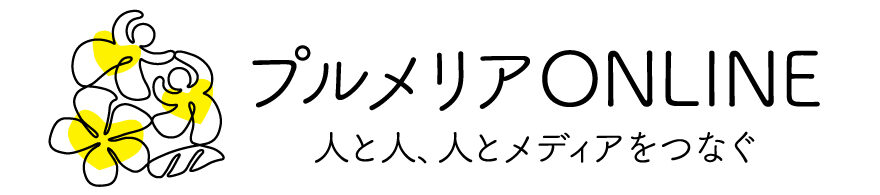道路陥没事故から間もなく3カ月―他のインフラ対策も「待ったなし」―
公益社団法人「日本記者クラブ」会員 長竹孝夫
(不動産経済Focus & Research 2025.4.23掲載)
埼玉県八潮市で1月28日に起きた下水道管破損が原因とされる道路陥没事故。発生から間もなく3カ月となる。今も陥没で落下したトラック運転手は救出されていない。下水道だけでなく、生活に欠かせない上水道などを含めたインフラ対策は大丈夫だろうか。早急に各地で点検し安全策を講じるべきである。
同県によると、今回の陥没事故は複数の要因によって下水道管が破損し、その亀裂から土砂が入り込み、地中に空洞が起きたことが原因とされる。汚水を迂回させるバイパス工事が現場で進められており、新規の恒久的なバイパス管を整備して下水道管を複線化する案も出ている。
県民の下水道料にも影響か
道路陥没事故の関連予算は、国からの補助金45億円と地方債45 億円で賄うとされている。大野元裕・知事は先の記者会見で「県民の下水道使用料に転嫁される可能性もあるが、事全体が見えない間は明確にいえない」と説明した。事故による影響は計りしれない。
国土交通省は、同様の事故を防ぐため、全国の古くて大きい下水道管を対象にした「特別重点調査」を行うと発表した。調査対象は直径2m 以上で、設置から30年以上の下水道管。約500の自治体や団体が管理しており、47都道府県で約5000km になる見込みだ。
上水道管の耐用年数は40 年
下水道とは別に、だれにも欠かせない上水道はどうか。水道管に詳しい作新学院大学(宇都宮市) の太田正・名誉教授は、筆者の取材に対し10年前「水道はあって当たり前、蛇口をひねれば水が出ると人は無意識に捉えているが、そうとはならない状況が刻一刻と迫っている。
都市でも農村でも各地で水道管の漏水や破裂事故が日常的に起きており、道路陥没や浸水被害も生じている」と語った。「主な原因は水道管の老朽化で、これに耐震性や場所的な特性が上乗せになる。人間に寿命があるように施設にも法定耐用年数があり、水道管は40 年とされている」と解説した。
水道は高度成長期に全国的に普及し、「寿命」を経過した経年管が急増する時期を迎え、2021 年度時点で22.1%である。増え続ける経年管の増加に、更新のスピードが追いついていない。
水道管の毎年の更新率は、わずか0.8%。このまま推移すると、水道管の更新は全国ペースでおよそ130年かかる。耐震適合率も36%程度で、配水本管ですら3分の2は耐震性が不十分な状態とされている。
水道管のトラブル年2万件
更新や耐震化が進まない理由は、大きく分けて二つ。まず費用の問題で、人口・水需要の減少による料金収入や国庫補助金の抑制を受けて必要とされる更新財源の確保が難しい。もう一つはマンパワー不足である。水道職員数は1980年代から約3割減少し、特に小規模な事業主体では1~5人に過ぎず、短期間に繰り返される人事異動もあって、技術継承はままならないという。
マンパワー不足の背景には、人口減少による収益減から、単純に職員を削減するという安易な対応はないか。職員自身も住民からの苦情や対応に耐え切れず、別のポジションを希望する。そうしたことが要因となっていないか。
事業体の長の課題は何か。水道は需給状況を含め地域によって事情が異なるが、各事業体の将来像( 中期・長期)の中に「水道の再構築」を明確に組み入れなければならない。つまり地域特性に合った水道システムをつくる必要があるのだが、大半がおざなりになっているとしか思えない。
すべての水道管を一斉に更新することはできない。優先順位を決めて延命措置を講じながら、「財政確保」と両にらみで進める。 場合によっては住民に丁寧に説明しながら合意形成をはかることも必要だろう。地方議員が住民とのパイプ役となることも大切ではないだろうか。
場合によっては、他の事業体と補完し合い、そこに県や国がもっと深く関与して人員や技術不足を補う必要もあろう。一つの地域で対応できない事態は、水道に至っては避けなければならない。これはだれもが考えることである。
関東の水道管状況をみると、40年を経過した経年化率は、神奈川、千葉、東京、埼玉、群馬が10%前後なのに対し、情けないことに更新率はどこも2%以下である。
全国では、水道管の破裂や水漏れなどのトラブルは年間2万件に及ぶ。45年経過の水道管が破裂し道路が冠水したケースもある。「朝、顔を洗い、トイレに行くといった日常生活。これが突然『遮断』されたらどうなるか。リスクは年々高まっている」「目に見えない対策こそ早急に取り組まなければならない」(太田名誉教授)
高度成長期の施設も老朽化
道路や橋、トンネル、学校、公営施設などの施設も老朽化している。高度成長期の人口急増から1970年代に集中して投資が行われたのが起因している。特に東京は関東大震災からの復興や東京五輪開催時(1964年)に建設されたインフラが多く、4割以上が老朽化しているとされる。特に利用頻度の高い首都高の延長約300kmうち湾岸部など約48kmは修理が急がれる。
インフラの対策を怠れば、今回の道路陥没事故のように「命」や「暮らし」に多大な影響を及ぼす。ひとたび大地震が起きれば拍車がかかる。もう猶予はないはずである。
関連リンク
不動産経済Focus & Research 刊行物一覧 (fudousankeizai.co.jp)
プルメリアでは多岐にわたるテーマとスピーカーによる講演・セミナーをアレンジしています。ご相談は、こちらよりお問い合わせください