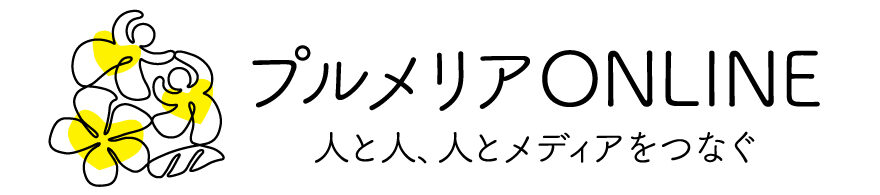認知症にも訪れる終末期 在宅医療、精神的サポートを
日本では、65歳以上の約6人に1人が認知症患者と言われている。一方で、認知症の病状はどのように進むのか、最期はどうなるのか、十分に知られているとは言えない。在宅医療に携わる医師として、現場で何が起こり、家族はどう理解できているのか、考えさせられる場面が多い。医師は治療する役割だけでなく、患者への伝え方や寄り添い方への工夫など、多くの課題が見えてくる。

「高齢者の健康に関する意識調査」(2012年:内閣府)によると、住み慣れた自宅で最期を迎えたいと考えている人の割合は54.6%に上る。
一方で、「人生の最終段階における医療に関する意識調査」(2018年:厚生労働省)によると、終末期医療・療養を自宅で受けたいと望む人の割合は50%を下回り、その中でも認知症の場合は14.8%に留まっている。
「死の瞬間は住み慣れた自宅で家族に囲まれて迎えたい」という反面、「その瞬間までの期間は、認知症の介護は大変だろうから家族に迷惑をかけたくない」という気持ちも推察できる。
ものわすれだけではない
認知症が進行するとどのような状態になり、どのように最期を迎えるのか。理解が少ないからこそ、認知症の介護に対する恐怖感が、ますます膨らんでしまうという人も多いのではないだろうか。
「緩和医療」や「終末期医療」というと、医療関係者でも悪性腫瘍すなわち、がんを真っ先に思い浮かべると推測するが、「認知症の緩和医療」「認知症の終末期医療」といっても、何をすればいいのかピンとくる医療関係者は多くはないと感じている。
しかし、認知症でも終末期は確かに存在する。分かりやすく言うと、認知症は進行すると新しい事を覚えられなくなり、周囲の出来事に対して正確な判断が難しくなっていく。その後、徐々に話せなくなり、歩くことも困難となり、最終的には食べることが不可能となる。
この過程で体が弱り、誤嚥性肺炎などの感染症で命を落とすことも多いが、合併症の危険を乗り越えても、最終的には食事や水分を取らなくなり、命を落とすことになる。「空腹である」ことや「食べるという動作の段取り」が分からなくなるからで、認知症は単にもの忘れ症状だけが進んでいく疾患ではない。
在宅医療に従事し、認知症終末期の患者を訪問することも多い。認知症終末期では、家族が愛情をこめて工夫した食事を口元に運んでも、口を閉じて全く受け付けず、ようやく口に入れたと思ってもすぐに吐き出してしまう。
このような現状を目の当たりにする家族や周囲の人たちにとっては、「食事や飲水ができなくなってしまったのは、私のせいではないか」と悩んだり、自身を責めてしまうことが多い。
しかし、病状が進むと誰にでも出てくる、認知症の症状の一つということを伝えると、自分を肯定し安堵してくれる。言い換えれば、認知症が終末期に至るまでの間に、「いずれは食べられなくなります」といった説明が、患者サイドに対して行われていなかったケースが散見されるのだ。
このように認知症も、がんと同様に進行すると死に至る、すなわち「終末期」が存在する疾患だ。
啓蒙活動の必要性
認知症患者の終末期については、痛みや息苦しさといった身体的な苦痛は比較的少ない。鎮痛薬や在宅酸素のような純医学的な治療が必要になるケースは少ないため、緩和医療・終末期医療のあり方の議論については、まだ発展途上という印象を持っている。
しかし、身体的な苦痛が少ないから問題ないとするのではなく、患者と家族の悩みや不安を引き出し、時には「一緒に悩む」といった精神的なサポートを「医者がやる」ことに大きな意義があると信じている。
すでに多くの自治体では、認知症を早期に発見し、必要な医学的・社会的な援助を早期に行うことを目的とした認知症検診などの事業が始められている。
認知症は多くの人が罹患する疾患でありながら、完全に治癒するような治療法の確立はこれからだ。今後、患者・家族だけではなく、広く社会へ向け、認知症の進行期・終末期を理解してもらう啓蒙活動の必要性が高くなってくる。
(Kyodo Weekly・政経週報 2022年10月10日号掲載)
掲載紙面PDF
筆者略歴
医療法人慶聰会 矢澤クリニック渋谷 院長
大湾喜行(おおわん・よしゆき)
1980年、東京都出身。埼玉医科大学を経て、昭和大学大学院医学博士。日本神経学会専門医、日本内科学会総合内科専門医。昭和大学藤が丘病院脳神経内科講師などを経て、2021年4月より現職。
関連リンク
プルメリアでは多岐にわたるテーマとスピーカーによる講演・セミナーをアレンジしています。ご相談は、こちらよりお問い合わせください